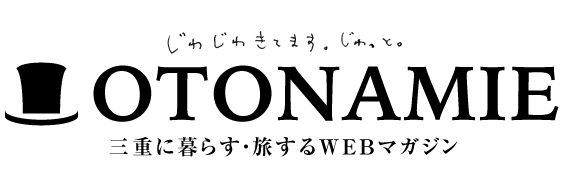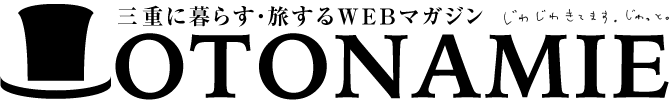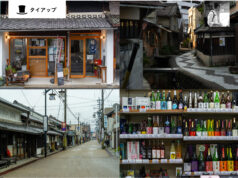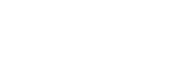全3回で綴る、伊勢志摩観光コンベンション機構(以下:コンベンション)が中心となり、地域の事業者と連携しながら進めているインバウンドを軸とした新しいまちづくり。
第1弾は観光を切り口に持続可能な未来のまちづくりに挑戦する狙いや想い、第2弾は同じ志を持つ仲間やグループとどのようにグローバルなまちにしていくのかを取り上げた。
本編、第3弾は、日本の人口減少や経済力の低下が背景にあり、国の成長戦略に位置づけられていているインバウンドの日本の各地での動きや伊勢志摩のポテンシャルについてに注目。
“まずインバウンドは、世界のデスティネーション(旅先)との競争になります。日本の観光業が30〜40年後、世界と戦って生き残れるか、今がまさに瀬戸際だと感じています”
そう話すのは観光庁やJNTOが中心となって実施している観光促進「ビジットジャパンキャンペーン」の企画・制作を数多く手がけ、現在は欧米富裕層向けの旅行会社「wondertrunk & co.」の創業者で共同CEO、岡本岳大さん。
今回、世界のインバウンドの市場や動向に詳しい岡本さん、伊勢市の前産業観光部長で地元の観光に32年携わってきたコンベンション専務理事の須﨑充博さんに伊勢志摩におけるインバウンドの可能性をお聞きした。
 岡本岳大さんプロフィール
岡本岳大さんプロフィール
●観光庁「サステナブルな観光コンテンツ強化事業」コーチ
●観光庁「地方部における観光コンテンツの充実のためのローカルガイド人材の持続的な確保・育成」有識者会議委員など
●金沢市「持続可能な観光振興推進会議」委員
など、政府自治体の委員・有識者などを歴任。
北陸、せとうち、そして伊勢志摩へ期待。
観光庁は「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり」事業で、高付加価値旅行者の誘客に向けて集中的な支援等を行うモデル観光地として、東北海道エリア、八幡平エリア、那須及び周辺地域エリア、松本・高山エリア、北陸エリア、伊勢志摩及び周辺地域エリア、奈良南部・和歌山那智勝浦エリア、せとうちエリア、鳥取・島根エリア、鹿児島・阿蘇・雲仙エリア、沖縄・奄美エリアの11エリアを令和5年度に選定し、山形エリア、佐渡・新潟エリア、富士山麓エリアの3エリアがが令和6年度に追加選定された。岡本さんに伊勢志摩以外のエリアの動きを聞いた。
岡本さん:「北陸エリア」や「せとうちエリア」は、実際にインバウンド客が増えつつあります。
北陸は漆などの工芸や加賀温泉など日本の文化で、せとうちは直島などの現代アートが外国人から人気なのだそう。岡本さんはインバウンドの増加には地理的な条件も関係しているという。

岡本さん:日本のインバウンド全体の傾向と同様、富裕層インバウンドも、東京・京都に滞在することが圧倒的に多いです。10日〜2週間ほどかけて日本に滞在するのですが、東京・京都から移動しやすい場所であることは物理的に案内しやすいです。いきなり離れたところにナビゲーションするのは、例えば北海道や沖縄の自然など何かに特化した興味を持っていない限り、現実的には難しい。東京から新幹線で北陸を経由して京都へ、またせとうちは関西圏からもう一歩だけ踏み込むというイメージです。今回選定された14の地域で、北陸、せとうち、そして私はその次に東京と京都の間に位置する、伊勢志摩に注目しています。
注目する理由は地理的な要因だけでなく「ビーチとは異なる海の旅先」という側面だという。
岡本さん:例えばカリブやモルディブなど、富裕層インバウンドの業界では、海があるリゾート地でゆったり過ごす旅のマーケットはとても大きい。世界で人気のある海の観光地はビーチです。伊勢志摩は島国・日本の海の文化が残り、ゆったりとできる上質な宿泊施設もすでにあるので富裕層インバウンドへの提案力があります。
伊勢志摩は風光明媚なリアス海岸にリゾート地がある一方、2000年以上の歴史を持つ海女漁が今も続いている。
岡本さん:持続性と歴史を兼ね備えた海の文化を深掘りしていけば、伊勢神宮の常若という日本人の精神につながっていきますね。海外でも事例がない魅力です。それをどう伝えていくのかが重要です。
そもそも世界を旅する欧米などの外国人にとって、最近こそ日本が旅先の選択肢に入るようになったが、大多数には東京、京都、富士山のようなシンボリックな場所しか認識されていないそうだ。
岡本さん:いきなり「海女さん」だけ細かく説明しても、ほとんどの外国人はピンとこない。イメージができないんです。
伊勢志摩で、新しい物語を紡ぐ。
伊勢志摩で外国人を招いたモニターツアーを多数受け入れてきた須﨑さんは、富裕層インバウンドは「ここにしかない本物」を求める傾向にあるという。

須﨑さん:海女さんにしても、大勢の観光客で観るショーや、獲った海産物を食べるだけでは物足りないそうです。予算を増やしてでも日本の文化や歴史など、本物に触れたいと考えています。
岡本さん:他の地域では、伝統工芸などの工房や酒蔵を巡るスタジオビジットやクラフトツアーが人気です。そう考えると海女さんと一緒に海に潜ったり話をしたり、海女さんの暮らしを体験することは、富裕層インバウンドにとって特別な体験になる可能性があります。
海の文化を深掘りする。海女さんと過ごす体験から伊勢志摩の海と山の自然の循環を知る。そして2000年のサスティナビリティが今も続く神宮や神道に触れる。そこには富裕層インバウンドに伝わるストーリー性が必要になるという。
岡本さん:外国人にとって式年遷宮は衝撃的です。20年毎にすべての社殿を作り直すことで日本の伝統や技術を未来につなぎながら、山の自然も再生させている。その山から命を育む水が流れ、海に流れ着く。それが1300年以上続いている。まさに日本の精神性の表れですよね。そこにたどり着けるように、どういう物語を旅行先を探す外国人に伝えるのか、今そこを考えることがとても大事な時期です。
須﨑さん:先日も富裕層インバウンドの旅行関係者を案内したのですが、その方は2回目の伊勢志摩でした。神宮で式年遷宮の話をしたら、とても驚いていました。1回目の時は教えてもらえなかったそうです。「それを早く知りたかった!」と、興奮気味に興味を持ってくれました。
日本の地方が連携すれば、世界と戦える時代になる。
これから日本の地方がインバウンドの誘客に力を入れていくなかで、富裕層インバウンドが思う地方のイメージはどんな感じなのだろう。
岡本さん:木造の寺院などの建物が多い、水がきれい、自然とともに暮らしている。そんな漠然とした印象だと思います。欧米は大陸なので海がないエリアも多く、海への憧れがあります。実は今回選定された14地域のなかで、島国である日本の海の文化を深堀りできる可能性として、伊勢志摩はとても可能性があると思うんです。
須﨑さん:伊勢志摩国立公園のなかで人が自然を大切にしながら暮らしている。それだけでも世界からすると珍しいことですね。
伊勢志摩といえば神道の聖地でもある。そのあたりの可能性はどうだろう。
岡本さん:チベットに仏教の精神性を求めていく人も少なからずいますし、ZENを求めて日本にいらっしゃる方もいます。でも世界的にはニッチな分野で、神道となるとさらに認知度は低いと思います。しかし核にある日本人の精神や自然とともに生きるサスティナビリティなどは変わらない。つまり深い魅力はあるので、自然や宗教の体験もマインドフルネスというカテゴリーから入ってくることが考えられます。
伊勢志摩にはここにしかない魅力がある。それを地域の目線ではなく、富裕層インバウンドの目線でどう見せるのか、どういうストーリーで伝えて興味を持ってもらうのかなど、今後の検討事項だと感じた。さらに懸念すべきことに、オーバーツーリズムがある。
岡本さん:オーバーツーリズムにはふたつの定義があると考えています。ひとつは「観光地が耐えらえる以上の観光客が押し寄せる状態」、つまり人数のキャパシティの視点。もうひとつは「観光客がもたらす負の部分に対処するだけの対価をもらえてない状態」と定義するものです。観光は違う文化のバックボーンを持つ人が来るので、良いこともあれば悪い影響も少なからずあります。来てもらった分、地域がそれを上回る対価をもらえるかどうか、それを地域の文化や自然の保護などに還元できるという視点も重要です。
さらに富裕層インバウンドの推進自体、オーバーツーリズム対策であるともいう。
岡本さん:伊勢志摩の観光客比率は、国内が97%でインバウンドが3%です。私はインバウンド客の人数を無理に増やしていく必要はないと考えています。インバウンドの人数だけ増えても、地域での消費インパクトがなければサスティナブルな観光地づくりにはつながっていかない。そのためにはインバウンドの消費単価を上げる必要がある。地域の事業者の方々はそれぞれに課題も抱えているので、みんながインバウンドに向く必要はないのですが、次世代を担う事業者の方々で興味のある方は今がチャンスと捉えて挑戦してもらいたいですね。そういった方々がジョインできる仕組みをすでにコンベンションが持っていることも伊勢志摩の強みだと思います。
須﨑さん:実はインバウンドに限ったことではないのですが、伊勢志摩で富裕層をターゲットにし、高付加価値なサービスを提供する宿泊施設は、すべてといってよいほど成功しています。すでにそのような事例がある地域なので、インバウンド事業に興味のある方は、ぜひ我々とご一緒させていただければと思います。事業者と伴走するのは、コンベンションとしてDMO(観光地づくり法人)のミッションでもあるのですから。
最後に岡本さんに、日本の地方全体のインバウンドの可能性について聞いた。
岡本さん:東京と京都だけでなく、北陸、せとうち、伊勢志摩のような地域が、高付加価値なデスティネーションとなっていくことは、地域経済の持続可能性にとって重要だと考えています。地域が、日本の魅力をさらに深く味わえる特別な体験を提供できるようになり、今回の事業を通じて、そういった連携体になっていくと、世界の観光市場で日本は存在感をもっていけると期待をしています。
伊勢志摩インバウンド
第一弾記事はこちら
第二弾記事はこちら
【タイアップ】
伊勢志摩観光コンベンション機構はインバウンドにご関心のある方々を歓迎しています。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
公益社団法人
伊勢志摩観光コンベンション機構
三重県伊勢市二見町茶屋二見町茶屋111-1
伊勢市二見生涯学習センター
TEL 0596-44-0800
ホームページ
YouTube
Instagram
X
Facebook
村山祐介。OTONAMIE代表。
ソンサンと呼ばれていますが、実は外国人ではありません。仕事はグラフィックデザインやライター。趣味は散歩と自転車。昔South★Hillという全く売れないバンドをしていた。この記者が登場する記事