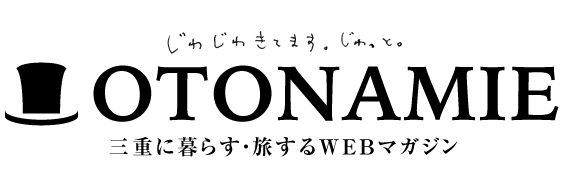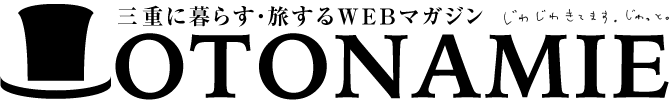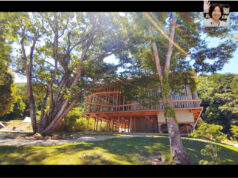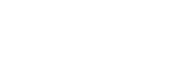三重県の中でも、リアス海岸の美しい景観、豊かな海から取れる食材など、多くの魅力を持つ伊勢志摩エリア。長きにわたり、旅行先として人気を集めてきた。
中でも国内外から参拝者が訪れる伊勢神宮。2024年にはおよそ750万人もの人が訪れ、コロナ禍以降は、インバウンド客、そして若年層の観光客も増えている。伊勢に訪れた人の中には、周辺の鳥羽市や志摩市へ宿泊する人も多く、順調に見える伊勢志摩の観光業。

そんな中で始まっているのが、「伊勢志摩高付加価値インバウンド観光地づくり事業」。伊勢市、鳥羽市、志摩市などの行政機関、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構が一体となって、高付加価値を求めるインバウンド客の誘致に向けた新たな取り組みだ。

コロナ禍以前の活気を取り戻しつつある今、なぜインバウンド客へのアプローチが必要なのだろうか。その問いに答えてくれたのは、伊勢志摩観光コンベンション機構(以下:コンベンション)の専務理事・須﨑充博さんとチーフ・加藤慎太郎さん。この取り組みの先に、地域にどのような変化がもたらされるのだろうか。
なぜインバウンド集客に取り組むのか
この事業がスタートしたきっかけは、志摩市の「もっと志摩の宿の魅力を知ってもらいたい」という思いから。志摩市には美しい自然を堪能できる高付加価値な宿泊施設がいくつもあり、国外の富裕層にもとても人気が高い。さらにこうした宿泊客を獲得するためにも、志摩市だけでなく、伊勢志摩エリア全体でのプロモーションが必要だと考えた。
そのエリア全体のプロモーションを担っているのが、須﨑さん、加藤さんが所属するコンベンションだ。実は、伊勢志摩地域のインバウンド客は全体の1~2%程度。国内からは幅広い年齢層の観光客が訪れる観光地でありながら、インバウンド客の誘客に向けた国外へのアプローチはまだ道半ばの状態だ。
なぜ必要なのか。その背景には、高齢化による地域社会の課題があり、日本人観光客だけに特化した観光業では将来的に成り立たなくなるという危機感がある。
須﨑さん:2100年には人口が今の半分以下の約5000万人になると言われており、今後は日本人観光客だけでは戦っていけません。観光客はもちろんのこと、担い手も減っていく。このような状況を見据えて危機感を持つ若手の経営者は、富裕層インバウンド客の獲得に向けて動き出しています。
では、どのように顧客を獲得していくのか。実は志摩市に宿泊している欧米の富裕層の中には、伊勢志摩固有の文化に興味を持つ人が多いという。
須﨑さん:世界を知っている富裕層の方々は、つくり込まれた観光体験では満足しません。だからこそ、伊勢志摩が持つ伊勢神宮や海女などの地域固有の文化や自然を体験してもらうことが大事です。ですが、十分な情報発信ができていなかったり、こうした方々が満足するようなツアーやガイドなどの受け皿が整っておらず、せっかくのチャンスを逃してしまっているのが現状です。
こうした課題を解消するため、コンベンションでは富裕層が参加できるモデルツアーや体験コンテンツの造成や、ガイドサービスの磨き上げに向けた取り組みが進められている。しかし、その目的は富裕層だけをターゲットにすることではないと言う。
加藤さん:富裕層だけを相手にした観光業を展開しようとしているわけではありません。富裕層向けの受け皿を整えることが、結果的にはシャワー効果で国内外のお客様の満足度向上にもつながります。さらに、地域の宿泊施設の稼働率を高めたり、担い手を増やすことができれば、廃業の危機にある宿も再生できるかもしれません。観光産業自体の生産性をあげることで、地域の文化や産業を持続させ、結果として伊勢志摩全体の価値を高めることにつながると思います。
須﨑さん:例えば、ハワイが一斉風靡したときと同じように、いつか伊勢志摩もみんなが憧れる場所になれるのではないかと思っています。ハワイも最初は芸能人や富裕層が訪れる場所でしたが、それがきっかけで広く人気を集めるようになりました。伊勢志摩も、まずは富裕層の方々に足を運んでいただくことで、その魅力が自然と広がっていくのではないでしょうか。
富裕層インバウンド客が求める「本物の体験」とは
では、その「高付加価値観光」はどのように実現できるのだろうか。コンベンションでは、富裕層を顧客に持つ海外の旅行会社やコーディネーターを招き、ともに伊勢志摩をまわりながら、どのようなニーズがあるのかを調査してきた。すると、ターゲットとなる富裕層インバウンド客は、単なる贅沢や消費ではなく、本物の体験や知的好奇心を求めていることがわかってきた。

須﨑さん:伊勢志摩は、海と山と川の間で養分が循環して、1つの生態系を形成している地域です。山から出た養分が海へ流れて、新鮮な魚や作物が取れる。自然の恵みに感謝して、伊勢神宮に奉納する。『今年もいい魚が取れました、お米が取れました』って。こうした文化がはるか昔から続いている、世界でも珍しい場所なんです。
加藤さん:伊勢志摩エリアは、大部分が国立公園に指定されているため、住人も協力して自然を守りながら共生しています。伊勢志摩国立公園が掲げる『海と山、食、人々の生活がどのように繋がっているのか』は、今で言ういうサステナビリティに通ずるところがあり、特に環境問題に関心の高いヨーロッパの方々には高い関心を示していただけました。
いわゆる特別なことではなく、生態系や文化から生み出される地域の「日常」をストーリーにして伝えることが重要だと、須﨑さんは話す。
須﨑さん:例えば伊勢神宮なら、20年に一度社殿を建て替えられること、そのための木が約150年かけて育てられていること。そういった歴史や背景を丁寧に伝えていくことであったり、海女文化を体験してもらうことだったり。海女小屋体験は国内旅行者にも人気が高いですが、欧米の方は食事よりも海女さんとの会話を重要視しています。『なぜ海女になったのか、どんな日常を過ごしているのか』海女さんたちの生きざまをもっと知りたいという声が多いです。これからは、こういったストーリーをどのように提供していくかが重要ですね。
地域資源を活かした体験型観光

日常を交えたストーリーを伝えながら、高付加価値な体験を提供している宿がある。志摩市にある「COVA KAKUDA(コーバカクダ)」は、真珠の養殖と加工を行う覚田真珠が手がけた宿。かつて養殖真珠の加工小屋だった建物を骨組みを残したままリノベーションし、4組限定のスペシャルな宿として生まれ変わらせた。
須﨑さん:真珠の生産量が減り、かつて使用していた小屋も使わなくなってしまった。このままではもったいないと思い、ここでしかない歴史や文化を伝えられる宿をつくり、もう一度ここから真珠産業を盛り上げたいというオーナーさんの強い思いから、この宿を始めることを決意されたそうです。
英虞湾を望むプライベートな空間を堪能するだけでなく、真珠貝の清掃体験、伊勢海老漁のエビ網外しと市場見学を通じて地元の暮らしに直接触れることができ、本物の体験ができると高い評価を得ている。また、スタッフ全員が食事の準備、受付、清掃といった業務をこなせる体制を整えており、全員で宿の運営を支えている。週休2日制を導入し、スタッフが無理なく働ける環境を整えている点も大きな特徴だ。
加藤さん:海のアクティビティやトレッキングなども宿のスタッフが担当し、お客様専用のコンシェルジュのような役割を果たしています。こうした体制があるため、富裕層のインバウンド客を受け入れ、高価格、高品質なサービスを提供できているのだと思います。
須﨑さん:こうした高付加価値なサービスをすべての宿が提供するのは難しいと思います。しかし、従来のサービスのまま利益をあげようと思うと、人手不足という問題にぶつかってしまう。伊勢志摩を観光地として持続させるためにも、低価格帯のパッケージだけではなく、少人数で高付加価値のお客様をターゲットにできるような体験を提供することも必要になってくるのではないでしょうか。
有名な観光地ではインバウンド客が急増し、爆買いをしたり流行を追うだけの観光客によって、地域住民の不満が溜まり、さまざまな問題が起こっているケースもある。だからこそ、あえて知的好奇心を持ち、文化や体験を通じて学ぼうする姿勢の外国人をターゲットにすることで、住民にとって暮らしやすいまちを守ることができるかもしれない。
地域の当たり前をインバウンド向けにデザインする

現在コンベンションでは、地域の方々とともに伊勢志摩を巡るモデルツアーや体験コンテンツの造成を造成など手口の創出やガイドサービスの向上だけでなく、既存のコンテンツやガイド、二次交通などの伊勢志摩の現状を把握するための調査も進めている。そこで見えてきたのは、案内ガイドや宿の人手不足。
加藤さん:現状の課題として、案内ガイドや人手不足が挙げられます。単にガイドや接客をすれば良いと言うわけではなく、富裕層に対応できるホスピタリティのある担い手がなかなか見つからない。外国人人材を活用して強化したいところですが、あまり受け入れ体制が整っていません。最も大きな課題は交通手段です。タクシーやレンタカーなどとの連携が遅れている状況です。
課題をクリアするためにも、まずは地域内での理解を進め、協力し合えるコミュニティをつくっていきたいと須﨑さんは話す。
加藤さん:富裕層インバウンド客という話をすると、自分には関係ないことだと捉えられることもあります。でも今回の事業は、次の時代のまちづくりなんです。伊勢志摩にある暮らしや文化、地元の人にとっての当たり前をインバウンド客向けに、デザインする。事業の核となる部分を丁寧に伝えて、事業者のモチベーションを上げていけたらと思っています。
須﨑さん:例えば伊勢志摩内で事業をしているけど、自分には関係ないかもと思っている人こそ、声をかけていただきたいですね。今この事業に関わってくれる地元企業は50社以上いて、色んな方たちと繋がり、ヒントをもらったり、行動できるための情報を得ることができます。プラットフォームを通じて繋がり、インバウンド客の誘致という機会をきっかけに地域をみんなで良くしていく。そんな繋がりでありたいと思っています。まずは興味を持ち、情報に触れてみることから始めてみてください!
伊勢志摩が目指す「高付加価値」とは、富裕層に限定したものではなく、広い意味で地域全体の価値を高めることを目指している。その取り組みは、地域の人とともに、固有の文化や自然を守りながら、次世代に引き継いでいくという大きな目標の一部なのだ。
伊勢志摩インバウンド
第二弾記事はこちら
第三弾記事はこちら
公開予定です。
【タイアップ】
伊勢志摩観光コンベンション機構はインバウンドにご関心のある方々を歓迎しています。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
公益社団法人
伊勢志摩観光コンベンション機構
三重県伊勢市二見町茶屋二見町茶屋111-1
伊勢市二見生涯学習センター
TEL 0596-44-0800
ホームページ
YouTube
Instagram
X
Facebook
OTONAMIE×OSAKA記者。三重県津市(山の方)出身のフリーライター。18歳で三重を飛び出し、名古屋で12年美容師として働く。さらに新しい可能性を探して関西へ移住。現在は京都暮らし。様々な土地に住んだことで、昔は当たり前に感じていた三重の美しい自然豊かな景色をいとおしく感じるように。今の私にとってかけがえのない癒し。