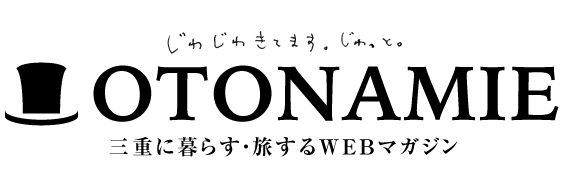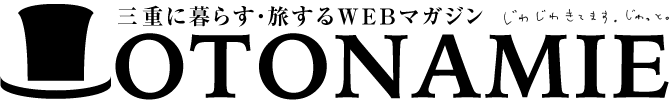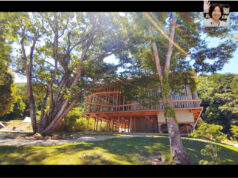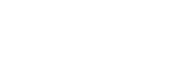全3回で綴る「伊勢志摩インバウンド」第1弾の記事では、伊勢志摩地域が富裕層インバウンドを加速させることで、観光を切り口に持続可能な未来のまちづくりに挑戦する伊勢志摩観光コンベンション機構(以下:コンベンション)の狙いや想いなどを取り上げた。
本編、第2弾では実際に地域の事業者とコンベンションが取り組み始めた体験プログラムなどを通じ、観光地である伊勢志摩がこれからどのようにグローバルなまちにしていくのか、またひとりではなく同じ志を持つ仲間やグループと一緒にまちづくりに取り組み、未来を切り拓く楽しさや可能性を取材した。
日本人の精神を、五感で体感。
“伊勢志摩には日本でもここにしかない特別な魅力があり、海外の方々の目線で伝え方や見せ方をアップデートしていけば、その魅力は理解してもらえると考えています”
そう話すのは今回取材をするひとり、コンベンションの専務理事、須﨑充博さん。コンベンションは官民が一体となり、伊勢志摩の観光情報の発信や企画など事業を通じて観光振興を行っている。

今回のコンベンションが進める「伊勢志摩高付加価値インバウンド観光地づくり事業(観光庁:地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり)」でタッグを組むのは、三重県指定伝統工芸品である神棚などの神具を製造販売する株式会社宮忠。
須﨑さんの前職は伊勢市の産業観光部長で、観光分野に32年携わってきた。宮忠の常務取締役、川西洋介さんとは10年以上の付き合いだという。

取り組みを始めたのは「自然を敬う神道の精神を身体で体験」というユニークなプログラムの造成。今はモニターツアーを繰り返しながら、ブラッシュアップを行っている最中だという。

内容は伊勢志摩の自然の中で神職にお越しいただいてお祓いをしていただいたり、神宮の「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」のように火鑽具(ひきりぐ)を使って忌火(いみび)を鑽り出す体験を行う。

また忌火は、森の中で行う精神集中や、自分でつくる注連縄の焼印にも使うなど、連続性を持たせることで神道における火の重要性を感じられる工夫もしている。
伝えたいのは、日本人の心。
観光に関わる産業ではない神具を製造する会社がインバウンド事業を始めるとは、意外性を感じる。きっかけはG7伊勢志摩サミットだったという。
川西さん:サミットの時、伊勢にも一時的に外国人が増え、まちに活気が出ました。しかしそれは一瞬で、その後は外国人をあまり見かけない元通りの日常に。このままでいいのかと何となく思っていたとき、旅行で京都に行ったらどこも外国人ばかり。食堂に入ればパートのおばちゃんやアルバイトの若者が「お米がなくなったので、うどんでもいいですか?」と、外国人に流ちょうな英語で話していたんです。驚きましたね。それ以降、他が外国人の受け入れができているのに伊勢は本当にこのままでいいのかという気持ちが膨らんでいきました。
そんなある時、須﨑さんがフランスで開催された観光系のイベントに出展するため、宮忠の神棚を持っていきたいと相談があったそう。
川西さん:英語版とフランス語のチラシを作ったんです。そのチラシを試しに伊勢の店にも置いてみたら、反応がとても良かった。外国人も神棚に興味があることがわかり嬉しかったですね。そうやって須﨑さんとは情報交換を続けていて、今回の事業を一緒にやらないかとお話をいただいたんです。
須﨑さん:外務省が運営して日本の食や文化を発信しているロンドンのJAPAN HOUSEで、数年前にそこで神棚や神宮、神道などを紹介したんです。神道は宗教でもあるし正直、外国人に嫌がられるかなと思ったらそうでもない。むしろ神宮の建築美、神聖さを感じる神棚のデザインにも興味を持ってくれました。印象的だったのが「日本人はなぜそのような建築物や常若の概念に辿り着いたのか」、「神棚に祈る日本人の精神とはなにか」など日本人の内面に興味を持ってくれたこと。そのとき「日本人の心のふるさと」と呼ばれる、伊勢志摩の強みを見つけた気がしたんです。そして外国人にとって、物や形のデザインが日本人の精神性に興味を持つきっかけになると確信しました。
精神的な豊かさを求める、新しい時代の価値観。

宮忠では2024年から、スタイリッシュな神棚などの神具の製造販売を始め、内宮前に「伊勢おきよめの店」をオープン。背景には伊勢志摩の観光客の層が広がったことにあるという。

川西さん:昔はご高齢の方が多かったのですが、今では若年層もとても増えました。今の若い方は、“心の浄化”や“お清め”といった事に関心があると感じています。昔ながらの神棚より、デザイン性の高い神棚などの神具を作って興味を持ってもらい「神様は目には見えないが、自分を高める」という神道の精神性を理解してもらえればと思います。それは外国人観光客も同じで、私たちが伝えたいのは「日本人の精神性」なんです。
須﨑さん:以前、南カリフォルニア大学に仕事で行きました。世界中からいろんな宗教の学生が留学しているのですが、特定の宗教にこだわりがないようでした。ただ、SBNR(Spiritual But Not Religious:スピリチュアル・バット・ノット・レリジャス)、直訳すると無宗教型スピリチュアルという人々が増えているそうです。特定の宗教は信仰しないけど、精神的な豊かさを求める層で、アメリカでは5人にひとりの割合だといわれています。そのなかで日本への関心は高く、禅や神道がもたらす精神的な豊かさも注目されています。
様々な宗教を受け入れる、神道の寛容な考え方に興味を持つ外国人も多いという須﨑さん。今回、造成している体験プログラムへの想いを教えてくれた。

須﨑さん:神道の方でなくても、海外から伊勢志摩にきて「神棚を伝統工芸品として、お土産に買って帰る」でも、私はいいと思うんです。まずは興味を持ってもらうこと。そして今回取り組むのは「モノ」ではなく、もう一歩踏み込んだ体験プログラム「コト」です。JAPAN HOUSEで感じた外国人の関心、またSBNR層が注目しているのは日本の精神です。そこへの需要は確信しているので、日本の精神を説明するだけではなく身体で体験することで、より深い理解と満足を提供できると考えました。

川西さん:体験プログラムでは注連縄や神棚を作るワークショップも検討しています。自分で作った大切な物を旅の記憶とともに家に飾っていただき、一過性ではなく日本の精神を思い出してもらいたいですね。
今から始める、新しいまちづくり。
体験プログラムのモニターツアーを実施し、感じていることを尋ねた。

川西さん:外国人モニターの方からも、満足度は高いと感じています。ただ日常的に神道に触れていないので、上手く伝わらないこともあります。実は私を含め会社には3名の神職がいるんです。神職として、神様と人の仲を取り持つ「なかとりもち」の精神も含めて、コンベンションさんとともにプログラムを磨きながら、外国人をはじめ多くの方に日本人の精神性を伝えられるよう改良していきます。でも私たちのような小さな会社1社では、発展性がありません。私たちが小さな歯車だとすれば、そのギアと組んでくれる人たちが現れたとき、地域に良い効果が出てくると考えています。まずは伊勢志摩で、次は全国のインバウンドに取り組む地域と一緒に展開できたら楽しそうですね。コンベンションさんからに背中を押してもらい、時にお尻を叩かれながらですが、確実にかたちにしていきたいです。
須﨑さん:私も背中を押し、宮忠さんには貴重な時間も割いてもらっているのだから責任は重大です(笑)。京都や飛騨には、外国人の方が感じられる日本らしい空間があります。伊勢志摩は「日本人の精神性」という強みがあり、コトに関わるポテンシャルは高いです。伊勢和紙や擬革紙、そして海女文化などもあり、これから地域をつくっていく世代の方々にはとても期待しています。今から様々な事業者さんや地域の方々とインバウンドに向けた新たな実験を繰り返しながら成功事例を重ねていき、グローバルの観光地として30年、40年先も世界のなかで生き残れることを目指しています。未来へのチャンスがある地域であることを伝えたいですね。
川西さん:外宮の前で生まれ育った私は、神道のある暮らしが当たり前すぎて、その魅力を発見できていなかった。須﨑さんに背中を押してもらい、コンベンションさんに体験コンテンツの造成をサポートしてもらって良かったです。
須﨑さん:伊勢志摩に暮らす自分たちの価値を見つめ直す。そして観光における付加価値を発見する。そうやって自らが動き出すことで地域が変わってくると信じています。今回の体験プログラムはそういった新しいまちをつくるスタートになれるように、努力していきます。もし「私だったらこういうことができる」と考えられる方は私たちと繋がりながら一緒に地域づくりをしていきたいです。ぜひ心当たりのある方はご連絡ください。
ワタクシゴトで恐縮だが、伊勢や熊野という聖地がある三重県に生まれてよかったと思うことがある。それはSDGsが提唱される遙か前、2000年のサスティナビリティを持つ神宮や日本人の精神を身近に感じられるからだ。
さて、2033年の「第63回神宮式年遷宮」に向け、今年から準備がはじまっている。オーバーツーリズムはごめんだが、式年遷宮までに外国人にも「日本が誇る文化や精神性」を伝え、2033年には観光客ではなく、外国人も参拝者としてお迎えできれば。そんなグローバルな時代の「令和版お伊勢参り」を想像してみたくなった。

自然への畏怖、そして畏敬の念を持ち、自然とともに生きてきた私たち「日本人の精神」が世界に受け入れられるのであれば、歴史が深い日本にはまだまだ眠っている地域資源がある。人口減少社会が加速する日本から世界へ向け、磨き上げた魅力を発信することができれば観光地における新たなまちづくりにつながり、グローバルなまちとして発展することもできる。今まさにコンベンションは様々なプレイヤーとともに、その可能性への挑戦を進めている。
伊勢志摩インバウンド
第一弾記事はこちら
第三弾記事はこちら
公開予定です。
【タイアップ】
伊勢志摩観光コンベンション機構はインバウンドにご関心のある方々を歓迎しています。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
公益社団法人
伊勢志摩観光コンベンション機構
三重県伊勢市二見町茶屋二見町茶屋111-1
伊勢市二見生涯学習センター
TEL 0596-44-0800
ホームページ
YouTube
Instagram
X
Facebook
村山祐介。OTONAMIE代表。
ソンサンと呼ばれていますが、実は外国人ではありません。仕事はグラフィックデザインやライター。趣味は散歩と自転車。昔South★Hillという全く売れないバンドをしていた。この記者が登場する記事