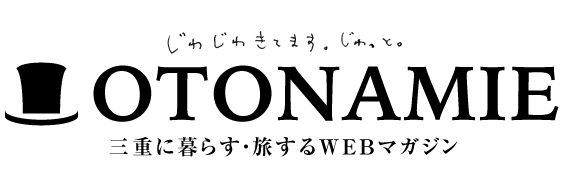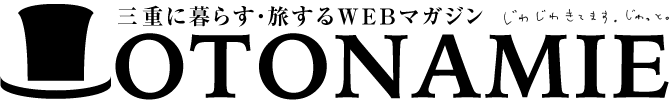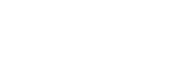朝の10時。桑名市住宅街の一軒一軒のポストに、郵便物を入れていく配達員の姿。ヘルメットには「かべたに」の文字。知る人ぞ知る、桑名で有名な郵便配達員の一日が始まる。
「おはようございます!」
軽やかな声とともに、赤いバイクから降りた配達員は、手際よく郵便物を整理している。
30歳、可部谷雄矢さん(以下可部谷さん)だ。
一見すると、どこにでもいる普通の郵便配達員だが、彼の名前が記されたヘルメットを見つめる住民たちの視線には、どこか熱い眼差しがあった。
「おお。可部谷さん!今度のレースはいつですか?」
犬の散歩中の老婦人が声をかける。
可部谷さんの顔がぱっと明るくなった。
「ありがとうございます。来月、鈴鹿で大きなレースがあるんです。頑張ります!」
そう、可部谷さんには二つの顔がある。
平日は日本郵政株式会社の桑名郵便局に勤める郵便配達員。
一方、週末になると、鈴鹿サーキットで時速300kmの世界を駆け抜けるライダーに変身するのだ。
可部谷さんは、国内最大級のバイクレース「鈴鹿8時間耐久ロードレース」(以下8耐)に3度出場し、国際Aライセンスを持つ本格派ライダーなのだ。
配達先のマンションで、住人の60代男性が手を振る。
「このあいだテレビで見たよ!今度こそ完走できるといいな!」
可部谷さんは笑顔で頭を下げる。
地元メディアでの露出により、彼の二面性は徐々に知られるようになった。中日新聞やJP CAST、最近ではSNSでも「日本最速の郵便配達員」として話題になっている。
時速300kmで駆け抜けるライダーが、平日は郵便配達員として制限速度を厳守し、安全運転に徹している姿は、アンバランス。しかし、だからこそ魅力を感じる人も多いのだろう。
今回は、郵便配達員の可部谷さんが、どうして鈴鹿サーキットに立つようになったのかをたずねた。
先輩への憧れから始まったバイク
小学校時代の可部谷少年は、自由奔放だった。
「かなり自由奔放で、周りに迷惑をかけることもしょっちゅうでした。学校に親が呼ばれたこともありました。」
そんな「やんちゃ」な少年には、1つだけ興味があった。
乗り物への強烈な憧れだ。
「幼少期から乗り物が好きで、特に車がすごい好きでした」
見るよりも乗る方が好きだったので、小学5年生になると両親とともに鈴鹿サーキット内の遊園地へ足を運ぶようになった。お目当ては、本格的なゴーカートだ。
後に彼は知ることになるが、この「乗り物好き」には実は、深いルーツがあった。
「僕が生まれる前に、父親と母親はモトクロスバイクに乗ってたみたいです。それを知ったのは結構最近なんですけど(笑)わざわざ言う機会もなかったんですかね(笑)」
可部谷さんは笑いを浮かべたが、言わずとして同じ道を辿った現実に、運命めいたものを感じずにはいられなかった。
中学生になると、両親と一緒に車のタイヤ交換をしはじめた。
「工具に触れるのが、すごく楽しかったんです」
工具に触れる楽しさから、高校は鈴鹿工業高等専門学校(以下鈴鹿高専)に進学した。
高校時代の授業で、印象深かったのは、1年生の時の鋳造実習だ。
「鋳造実習では、鍋敷きを作ったんです。漢字で“鈴鹿高専”って4文字で書いて型を作り、その形状にアルミを溶かして固めるっていう作業です」
鍋敷きを作る。一見単純に思える課題だが、その製造工程は本格的だった。型作り、溶解、鋳込み。一連の工程を自分の手で体験する感動は、今でも鮮明に覚えていた。
「鍋敷きってところがシュールですよね。まだ実家にあると思います、多分。」
可部谷さんにとって「自分でものを作る」初めての経験だった。
時を同じくして、バイクとの運命的な出会いがあった。
1つ上の先輩が乗っていたのは、ホンダのVFR400R。1992年式という、当時でも10年以上前のバイクだった。
しかし、その古さこそが魅力だった。
バブル時代の贅沢な設計思想で作られたマシンは、コストパフォーマンスを度外視。同じ排気量でも現代のバイクを凌駕する圧倒的な速さを誇っていた。
高校の前を駆け抜けていく先輩の姿。
エンジンが唸りを上げ、一気に加速して走り去っていく光景は、18歳の可部谷さんの心に深く刻まれた。
「すごく、かっこよくて。憧れました。」
憧れを現実にするまでに、時間はかからなかった。
免許を取る前に、可部谷さんはバイクを購入した。
NSR250R。
先輩とは異なる2サイクルエンジンを搭載した、これもまたバブル期の名車だった。4サイクルの2倍の爆発回数を誇るエンジンは、理論上2倍のパワーを生み出す。
「これだったら先輩に勝てると思って(笑)」
そんな単純で純粋な動機だった。
車が大好きだった幼少期。
タイヤ交換から芽生えた工業関係の学問への興味。バイクへの憧れ。
そして「バイクに乗り続けたい」という思いから、日本郵政株式会社への就職を決めた。
楽しむことは最強の武器、敵なしの3年間
一度サーキットから足が遠のいていたが、22歳のある日、再びサーキットに降り立った。
愛車のNSRを引っ張り出し、久しぶりにエンジンをかけた時の感動を、今でも覚えている。
とはいえ、郵便配達員として働いていた可部谷さんは、その当時、ライダーになろうという野心はなかった。ただ、バイクを楽しみたいという思いだけだったからだ。
鈴鹿ツインサーキットでの走行が日課になり、バイクで駆け抜ける時間はただ「楽しい」ものだった。
「楽しい。ただそれだけで、続けていました」
レースへの出場も、楽しさの延長にあった。
3年間ほぼ「敵なし」の状態が続き、表彰台の常連となりチャンピオンも獲得したが、全ては「楽しさ」からだ。
転機となったのは、愛知県岡崎市のバイク店が運営する『CLUBモトラボEJ』からのスカウトだ。
600ccクラスへの挑戦を勧められた。
そして、2020年本格参戦の初年度でシリーズチャンピオンを獲得。
翌年には京都市山科区のバイクショップ「山科カワサキ」が母体の『山科カワサキKEN Racing』に迎えられ、鈴鹿8耐への道が開かれた。
灼熱の鈴鹿、8時間の戦い
鈴鹿サーキットの8月は地獄だ。
気温37度、アスファルトの路面温度は65度に達する。
ライダースーツに身を包んでバイクにまたがることは、灼熱のサウナの中で激しい運動を続けるのと同じだった。
8時間耐久レース。
3人のライダーが1台のバイクを交代で駆る。
1人あたり約50分を3回、計2時間半を走り抜ける。
あまりの過酷さに、50分のレースが終わるごとに、体重は2キロ減るという。待機時間は回復との戦いだ。
失った2キロ分の水分と栄養を、次のスティントまでに補わなければならない。フルーツ、ビタミン、クエン酸。消化に良いものを選んで体に流し込む。
体重が戻らないまま乗れば、栄養不足で操作がおぼつかなくなる。熱中症の危険もある。
しかし、8耐の魅力を可部谷さんはこう語った。
「8時間の耐久は長いですが、実はもっと長い8ヶ月があるんです」
レースの準備は1月から始まる。
30名ほどのチーム編成で臨む一大プロジェクトだ。
監督、ライダー3名、メカニック10名、事務担当、ケータリング担当、トレーナー。それぞれが専門分野で力を尽くす。
バイクは市販車をベースに改造する。
エンジン、サスペンション、ブレーキ。すべてがレース仕様に生まれ変わる。
セッティングを何度もテストを重ね、ミリ単位で調整していく。
可部谷さん自身も体作りに励む。
炎天下でのランニング、サウナでの暑さ慣れ。
郵便配達で培った体力に加え、8耐に特化したトレーニングを積んだ。
そんな長期間の準備を経て迎える決勝レースでは、チーム全員の想いが一つのバイクに込められる。
とはいえ、8耐はそんなに甘いものではない。
2022年は決勝当日のコロナ感染でリタイア、2023年もチームメイトの転倒でリタイア。
二度の悔しさを経て、可部谷さんの心境が変化し始めた。
「今までは楽しむことがメインでしたが、2度のリタイアを経験して、”完走したい”と明確な目標ができました」
2025年8月。3度目の8耐挑戦。
今回は『EDWIN GESUNDHEIT Racing』から出場したが、予選で可部谷さんは転倒してしまった。
「こんなに悔しかったのは初めてです。悔しいのは、”楽しい”の先に”勝ちたい”があるからなんですよね」
決勝には進めたものの、可部谷さんの心には悔いが残った。
幸い、8耐では2台のバイクを持ち込めるためもう1台で決勝に出場したが、結果は再びリタイア。
30名のチームメンバーの8ヶ月間の努力。応援してくれるスポンサーの期待。それを背負って走る責任の重さを可部谷さんは痛感した。
「目標は、8耐を完走することです。
そして、できるだけ長く多く8耐に出場したいです」
楽しさから始まった物語に、いつしか勝負への執念が加わった。けれど、可部谷さんを支え続けているのは今も変わらず、バイクに乗る純粋な喜びだ。灼熱の鈴鹿で味わう8時間は、その究極形だった。
noteに熱中している31歳。店舗取材や人物インタビュー・コラムを中心に執筆。18歳まで三重県桑名市で育ち、大学進学を機に愛知へ移住。一児の母。