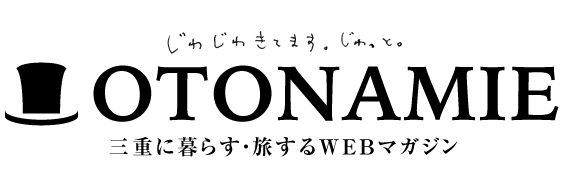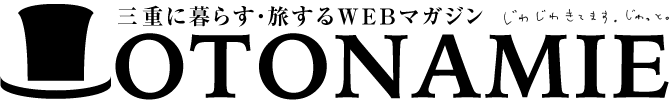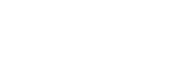用があるわけでもないのに、
どうしようもなく人と話したくなることがある。
そんなときはふらりと家を出て、
最寄り駅前の商店街を彷徨ったりする。
それでお気に入りの場所を発見したら、
二回目は好きなあの子を飲みに誘う。
もはや行きつけの店で、
あなたはこんなセリフを言うかもしれない。
「マスター、いつもの」
人は、自分の居場所を求める。
電信柱にとまる小鳥たちのように。
なぜ彼は、マスターと呼ばれるのか。
早朝、一台の軽トラックがやってきた。
目の前に海が広がる漁師町には、船の音が響いている。
ここは南伊勢町・阿曽浦。
一時は真珠養殖で隆盛を極めた土地だ。
阿曽浦にも、マスターがいる。

地元の魚屋で配達の仕事をしつつ、カニ網漁を営む。
こよなく酒を愛し、休みの日は旧友と飲んだくれる普通のおっちゃん。
なぜ、彼はみんなからマスターと呼ばれるのか。
このことには深いわけがある。
そう。
これは激動の時代を生き抜いた、
ひとりの男の人生物語。
この話を聞いたら、
あなたもきっと彼を「マスター」と呼ぶに違いない。
物語の始まりは、今から五十五年前に遡る。
〜阿曽浦編〜
阿曽浦で「幻の」卒業生。
阿曽浦で唯一の中学校が消えた。
マスターが中学三年生の時だった。
度会郡南島町立中島中学校。

「ここに中学校があったんやけど。
もう住宅地になっとるでさ」
そう語るマスターは、
中島中学で勉強した最後の生徒である。
マスターが卒業する年、
すでに南島中学校として他校との統合が済んでいた。
しかし、南島中学は校舎どころかグラウンド整備もまだだったため、
南島中の生徒ではあったが、中島中学の校舎で勉強した。
南島中学校中島分校。
そう書かれた卒業証書は、「幻の卒業証書」と言われている。
廃校になった中学校。
昔あって、今はないもの。
阿曽浦はそんなもので、溢れてる。

地元に仕事がなかった。
マスターの家は、真珠養殖を営んでいた。
真珠の玉を入れる母貝(ぼがい)を育てる仕事だ。
家業の手伝いをしていた小中学時代は、決して良い思い出だけではなかった。

「母貝養殖っていうのはきつい仕事やったよ」
学校から帰ってきても、仕事が終わるまで遊びに行くことができなかった。
弟と一緒に、貝掃除や網直しの準備をこなした。
冬場の海老網漁こそ辛かった。
学校が休みの日は朝から起こされて、寒さで指がちぎれる思いをした。
小さい頃から親の働く姿をみていたからこそ、
子どもながらに感じることがあった。
「貝掃除は船で屋形を引っ張ってって、海の上で作業しとった。
船が通るたびに揺れて、風に吹かれて、船酔いするんやって。正直な話、僕に漁業は無理やって」

違う仕事をするには、外に出るしかなかった。
当時の中学生に与えられた選択肢は、今とは比べものにならないくらい少なかったのだ。
「本当は高校に行きたかったんやけどさ。
親の苦労もわかっとったもんで」
中学卒業というタイミングで、生まれ故郷である阿曽浦の地を旅立つことに決めた。
〜上京編〜
想像すらできない、よその暮らし。
マスターが目指した場所は、大阪。
正確には目指したわけではなく、そうせざるを得なかったと言うべきかもしれない。
親戚のおばの嫁ぎ先がたまたま大阪の洋服屋で、
そのつてを頼りに大阪へ転がりこんだ。
都会への憧れなど微塵もなかった。
テレビもない時代、自分の住む土地以外を知るよしがなかった。
とにもかくにも、不安だらけ。
「どういう仕事かもさっぱりわからんわけでさ。
いっぺん夏休みでも何でもいいで来てくださいって向こうが言ってきて。親父に連れられて、大阪のおばさんのとこへ行ったんさ。
そこまでの道順を書いた紙を握りしめて、
この列車に乗って、このバスに乗ってって。そしたら建物はすんごいし、信号はいっぱいあるし」

大阪の道頓堀で、アワビやサザエが高級料理として売られていることに驚いた。
「僕らは子どもの頃から、サザエやアワビなんか自分らで食べたいだけだべてさ、
あとは蹴飛ばして遊んでたりしてたわけやでさ」
住む場所がどんな場所で、自分はこれからどんなことをするのか。
そんなことさえもわからず、ただこれから行く場所を記す紙を握りしめて。
彼が感じていた不安は、ネット社会で生まれ育った僕には想像もできないだろう。

職人の道を生き抜く覚悟。
大阪で洋服屋の仕事が始まった。
紳士服のあつらえという、職人の道を進むことになった。
自分が希望して就いた職ではない。
裁縫なんてやったこともないから、一から習いはじめた。

マスターを待ち受けていたのは、
職人の世界の強烈な縦社会だった。
「その当時は夕飯があったかいご飯やったん。
次の日の朝に残りのご飯をお茶漬けで食べる。でも、職人の先輩らがほとんど食べてしまうで、
僕らは全然食べれんくて昼までお腹空かせてることが多かった。昼飯は自分で用意せなあかんで、
お金がないときは恥ずかしい話、デパートの試食品コーナーでしのいでたんや」
当時の職人たちは、
五年もの月日を「見習い」として過ごさなければならなかった。
しかもその五年でズボン・上着のシングル・ダブルと一通りができるようにならなければ、
一人前として認められることはない。
安い給料で生活しながら、仕事以外の時間もあつらえの練習に充てた。
「自分で仕事が終わった後、古い洋服を貰ってきてそれを一からバラくんですよ。
どっから縫ったら服の形になるんか。
どういう風に縫ってあって、中にどういうもんが入っとるんか。一つずつばらいてくと、今度は縫うときがその逆になるわけやでさ」
職人の道の厳しさに耐えられず、辞めていく仲間たちもいた。
「一年目でやめてく人らもようけおったで。
初めのうちは仕事を習うっていうよりも下働きが多かった。朝起きて、トイレ掃除して、親方の車を洗うだとか、店を雑巾掛けしたり。
しもやけだらけやったで。そういうのが厳しいっていうので、辛抱せん子らはもう辞めてったな」
しかし、マスターは絶対に辞めないと心に決めていた。
「親戚の紹介で行ったもんで、何があってもやめられん。
迷惑かけたらいかんもんで」
五年間、見習いとしての修行を終え、その後一年間は礼奉公(れいぼうこう)。
礼奉公とは、お世話になったお店への恩返しとして、六年目を見習いの給料で働く文化だ。
中卒で大阪へやってきてから七年、二十二の歳。
マスターはようやく一人前の職人となった。

自分の人生の可能性を探す。
自分が作った紳士服を、一着いくらという値段で買ってもらう。
お金ができたから、アパートも自分で借りた。
仕事に余裕ができてきた頃から、
マスターは自分の人生について考えはじめた。
「このまま大阪で頑張っとっても、職人で終わりやな」
一人前になるということは、
無限に広がる自分の可能性に区切りをつけることでもある。
大阪に来て十年目の年。
もったいないという周りの声を押しのけ、マスターは故郷へ帰る決断をする。

〜望郷編〜
帰り道の出会いは突然。
伊勢まで帰ってきた。
地元・阿曽浦までのバスが来るまで、幾分かの時間があった。
暇を潰すためにパチンコ屋に寄ってみると、
そこにいたのはなんと、中島中学時代の同級生だった。
地元に帰りたいが、なにか仕事はないだろうか。
マスターの話を聞いた彼が紹介してくれたのは、
伊勢市内のお好み焼き屋だった。
「お好み焼きか、いいなって。
野菜嫌いやったんやけど、キャベツは食べれたもんで」
大阪時代の思い出でもあったお好み焼きに、なぜかとても惹かれた。
マスターは伊勢で働きはじめることになった。
再び始まる見習いの日々。
お好み焼き屋で働きはじめると、
今度は一からその作り方を学ぶ日々が続いた。
「一番最初の練習は、
雑巾をぎゅうっと絞ってからお好み焼きの出来上がりの大きさに切って、
それをコテで返す練習。それを店が終わってからあくる日もあくる日もやったで」

お好み焼きを作る以外にも、マスターには仕事があった。
マスターが働く店は松阪に支店があり、
伊勢から車でお好み焼きの材料を運んでいた。
その配達の仕事の最中、マスターに惨事が降りかかった。
当たり屋に狙われたのだ。
「大雨の時にバンっと。
ハンドル切って対向車に当たらんように思いっきりハンドル切ったらさ。
端っこの岩盤に激突して、車がパー。目撃してくれとった人がおって、
その人が当たり屋を追ってくれとったんやけど、人混みでわからんようになって」

車は大破した。
目撃者が連絡をとってくれたおかげで、すぐに社長が駆けつけてくれた。
しかしその第一声は、マスターが想像しないものだった。
「車は大丈夫やったかって。
こっちの身体は心配せんと。車の状態はみたらわかるやろって」
社長への信頼が、揺らいだ。
社長との関係、そして決別。
次の日からも、配達の仕事は続く。
電車と徒歩で配達の仕事をやりくりする日々。
材料や器具を包んだ風呂敷を抱えて歩いた。
マスターの体力はもたなかった。
自分の給料から天引きしてもいい。
新しい車を買ってくれ。
マスターの直談判は社長に受け入れられなかった。
「あんた自分で車壊したくせに何言うとんやって。
そう言われて、もうカチンときてしもうて」
その時はちょうど正月前。
ボーナスをもらった直後だった。
「お金をとって辞めてくんかって。
何をこんな端た金って、全部投げ捨てて出てきてしもうた」
社長との喧嘩別れ。
まっすぐに生きてきたマスターだからこそ、許せないことがあった。
職を失ったマスターは、
当時足繁く通っていたスナックのマスターの店へ転がりこんだ。
料理の道のはじまり。
スナックという夜の商売へ足を踏み入れたものの、
そこは客にお酒を振る舞うだけでなく、料理の味にこだわりのある料理屋でもあった。
ピラフ・スパゲティ・手羽先。
メニューにある料理をひとつずつ覚えた。
お店の味の基本は、手作りのデミグラスソース。
「野菜と肉を入れた後、火をかけて煮詰める。
夜に人がいない間は、なんかあるといかんで換気扇つけて弱火にして、
人がある間は強火にして。デミグラスソースの素になるものを作るんに一週間かけた」
味の評判も良かった。
このスナックでの経験が、マスターを飲食の道へ導くことになる。
突然訪れた親の死。
料理の仕事にのめりこむマスターに、またもや悲劇が襲った。
地元・阿曽浦に住むおじから、突然アパートへ電話がかかってくる。
マスターの父親が働いていた工場で事故があった。
工場にいた何人かが、あかん。
電話口でおじは、彼にそう告げた。
マスターはすぐに父親の職場へと向かった。
「滅多に連絡してこんおじさんから、伊勢のアパートに電話がかかってきたもんで。
これはひょっとしたら、親父はひょっとしたらって」
マスターの予感は的中した。
病院にいた父親の姿を見た時、出てくる言葉はなかった。
「病院のベッドの上で、
膝抱えた状態ででがんじがらめ。当時はまだ土葬やで、身体が硬直してくるといかんで棺に入る形で縛られとった」
マスターは当時二十七歳。
葬式の準備をするために、阿曽浦へ帰ることになった。

〜帰郷編〜
ついに地元へ帰ってきた。
阿曽浦に到着したはいいものの、母親がいない。
いや、いないわけではなかった。
見つけられなかったのだ。
「最初はどこにいるかわからんもんで。
親戚の人らに聞いたら、そこにいるやないかって。見たらもう、どこのクソババアかいねって」
母親の姿は、変わり果てていた。
精神的なショックで、髪は真っ白になっていた。
前日に家から送り出した父親が、
あくる日に死んで帰ってきた。
その悲劇が、母親を老婆に変えてしまった。
「これはほっとかれんわって。
伊勢も阿曽も変わらんで、もうこっちで仕事しようと思った」
父の死と、残された母。
今まで自分を育ててくれた親の存在が、マスターを地元・阿曽浦へ引き戻した。

マスターがマスターになるまで。
地元で働くとなると、就職先はごくわずかしかない。
しかも、大半は海の上の仕事だ。
阿曽浦で何をすれば、食っていくことができるか。
マスターの覚悟は決まっていた。
自分の店をひらくという、夢。
しかしそんな若者の夢の前に、時代立ち塞がった。
「すぐにでも店建ててやろうかいねって思ったんやけど。
当時は住宅金融公庫っていうのが申し込んでもなかなか当たらんもんで」
今では考えられないが、
真珠養殖が盛んな頃の阿曽浦の地価は、とんでもなく高かった。
住宅ローンの金利も跳ね上がっていた当時、
阿曽浦にお店を建てるには相当なお金が必要だった。
とりあえず、神前浦(かみざきうら)という隣町のバーに勤めることにして、
お金の算段がつくのを待った。
昭和五十二年八月。
満を持して、マスターは自分の店を始めた。
地元の人たちの憩いの場を作る。
店の名前は、とまり木。
「店の前にある電信柱に、スズメやツバメがようとまっとっるのを見てな。
お客さんがようとまってってくれる店になってほしいって思ってな」

マスターの願いは通じ、
店は繁盛した。
天気の悪い日は仕事休みの漁師たちが朝から店に集い、
手拍子で歌謡曲を一番から三番まで歌った。
真珠養殖で帰りが遅くなる両親から電話がかかってきて、
家で待つ子どもたちのところまで料理を配達した。
盆正月は町から帰省してきた人たちが、
コーヒーを飲みにやってきた。
とまり木は阿曽浦の人たちの憩いの場となり、
マスターはいつしか、地元の住民たちから「マスター」と呼ばれるようになった。

自分の味、とうふステーキ。
伊勢のスナックで培った料理の腕は、
とまり木のメニューに引き継がれた。
ラーメン・チャーハン・カツ丼・スパゲティ。
マスターが作る料理は、おいしいと評判が立った。
一番の人気メニューは、とうふステーキ。

「伊勢におった時、スナックのマスターに居酒屋連れてってもらって、
どういうもんが売れとんのかってな。その時名古屋でとうふステーキが流行っとったもんで、
どんなもんか片っ端から食べとった。無類の豆腐好きやったもんで」
とうふステーキといっても、いろいろな味があった。
試行錯誤の上、最終的には和風だしで自分好みの味に仕上げた。
店で出すやいなや、人気が出た。
もともとは冬限定メニューだったものが、お客さんの要望で通年メニューになった。

〜最終章〜
時代の変化と、とまり木の最後。
とまり木は、三十五年間続いた。
過去形で語らなければならぬのも、実はとまり木は六年前になくなってしまっている。
マスターを襲ったのは、またもや時代だった。
減り続ける阿曽浦の人口。
それに追い打ちをかけるかのようなバブルの崩壊。
決定打となったのは、飲酒運転の摘発の激化だった。
客足はめっきり減った。
「ちょっとでも店の足しにって、
知り合いが社長をやってる土建屋に入れてもらった。それから三年くらいは、
土建屋の仕事から帰ってきたらすぐにシャワーを浴びて、
お客さんがおる時は裏から入って店出とった」
とまり木を守るために二足のわらじを履いたマスター。
しかし、決断の時は迫っていた。
「もう借金もなくなっとったでさ。
また借金作るよりは、さっと廃業した方が賢いなと」
とまり木、営業最後の日。
お客さんを大勢呼んで盛大にやろうかとも思ったが、
誰に惜しまれることもなく、ひっそりとやめることにした。
「おれは声かけられんかったとか、
あの人は呼ばれなかったとか、
そういうのがあるといかんと思ってな」
とまり木の最後は、
マスターが静かに看取った。
マスターは、何を思う。
当時のことを淡々と語るマスターの言葉から、
その心中を察することは難しかった。
しかし、きっとそれは苦渋の決断だった。
わけもわからず故郷を出て、大阪という大都会で自分の可能性に挑み、
一人前として認められた自信を抱えて料理の世界へのめりこんだ。
そして親の死をきっかけに阿曽浦に戻り、開いた店。
それがとまり木。
マスターの人生そのもの。
その店を閉めるという決断を、自分自身で下した。
そのことの意味を、僕はまだ理解できない。
ただその重みを、嚙みしめる。

とまり木とマスター。
いま、マスターは阿曽浦の魚屋で配達とカニ網漁を営んでいる。
魚屋のほうは、中島中学時代からの朋輩・橋本剛匠の会社だ。
取材の最後、とまり木の店の名残を撮影している時、
マスターが声をかけてきた。
「国破れて山河あり、やろ」
その言葉を聞いた時、
なんともいえない想いがこみあげてきた。
とまり木があった時代を、僕は知らない。
しかしそこに残るものは決して「山河」だけではなく、
とまり木という店があったことは、変わりようのない歴史の一部。
自分の知らないところで、
でも自分が生きているこの世界で、
自分の知らない物語がいくつも生まれ、
そして消えていく。
もはや語られることなく人間の胸の奥にしまわれた物語が、
あとどれくらいあるのだろう。
誰にも知られることのない物語は、
誰かを勇気づけたり、感動させたりすることだってできるかもしれない。
それなのに……。
これは激動の時代を生き抜いた、
ひとりの男の人生物語。
こよなく酒を愛し、休みの日は旧友と飲んだくれる普通のおっちゃん。
でも、近所の人からは「マスター」と呼ばれている。
そうだ。
今度はあの人の話、聞いてみようかな。
三重県南伊勢町の漁村に移り住み、漁師&情報発信をしていました。現在は県外在住。