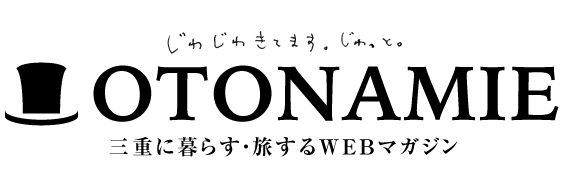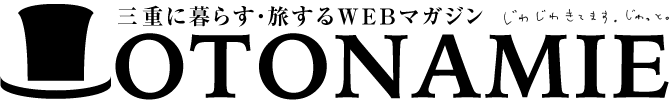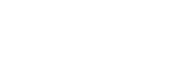僕はワカメの味噌汁が好きだ。
ワカメが好きなわけではない。
でも、それを食べると浮かび上がる光景というものがある。
母さんが作ってくれた。
それが僕にとっての家庭の味だった。
味噌汁には思い出を呼び起こす力がある。
そうは思わないか。
味噌汁の味噌。
そしてその素材となる糀(こうじ)をつくる男の話。
鬼の伝説が伝わる村へ行く。
鬼が立っていた。
鬼なら鬼らしくトラ柄のパンツを履けばいいものを。
彼が着ていたのは白のブリーフだった。
ここは南伊勢町・押渕(おしぶち)。
鬼の住む洞窟があるという。
日本の農村。
田園風景が広がる。
狭い道を車で進んでいくと、大きな倉庫がみえてくる。
ここに、米糀をつくる男がいる。
鬼の居ぬ間に、話をきこう。
庄下糀屋五代目・庄下真史(しょうか ただし)。
二児の父であり、この糀屋の主人。
家業を継いで、今年で十年目になる。
和の味の代名詞・糀(こうじ)。
糀とは、味噌や醤油・みりん・清酒などを作るために必要な原料だ。
言わずもがな、糀がないと和の味は表現できない。
庄下糀屋では米糀を育て、それを原料にして味噌をつくっている。
蒸した米を冷ましたものに、種糀を混ぜ込む。
種糀とは糀の赤ちゃんのようなもの。
それらを室(むろ)で保管すると、だんだんと糀が育ってくる。

糀が育つとは、発酵するということ。
微生物がお米を分解することで、糀は増えていく。
糀づくりは、生き物の世界だ。
庄下糀屋は、手作業と自然発酵にこだわり続ける。
機械で一律に管理するのではなく、あくまで自然発酵で温度を調節していく。
寒そうなときは毛布をかける。
必要ならストーブをおいて、室を温める。
暑そうだったら、ドアを開けて風を入れる。
ヨーイ・ドンで同じことやっても、温度によって育ち方が違う。
だから、糀の声に耳を傾け、育ちやすい環境を整えてあげないといけない。
「生き物なんで、こいつらも
(小さくて)みえないだけで」
そう語る真史さんは、糀と言葉を使わない会話をしている。
糀を育てる姿勢は、我が子を見守る親そのものだ。
ただし、手をかけすぎることが良くないのは人間と同じ。
「常に触るのはあんまりよくないですよ。
今からさあ育とうと思っとったところに、また手をいれられると嫌じゃないですか」
なるほど。
庄下家の糀はのびのびと育っている。
仕事は子どもの頃に「遊び」で覚えた。
真史さんは大学入学と同時に東京へ行った。
東京農業大学短期大学部醸造学科。
遠く離れた土地にいても、頭の片隅には家族の仕事があった。
醸造という学問を選んだのも、故郷・押渕の記憶が絡む。
「家業なので、ちっちゃい頃から母さんの後ついて配達に行ったり、田んぼで遊んだりしとった。
それこそ自分とこの米を食べて育ってきた。
仕事としてではなく、
遊びとして仕事を覚えていたので、
こんなことしとった、あんなことしとったなというのを思い出しながら今も仕事をしとる」
意識せずとも、記憶のなかに刻まれるもの。
実家で「遊びながら」得た原体験が、真史さんの道しるべとなっていた。
「東京でご飯を食べに行って定食を食べた時に、味噌汁が合わんもんで。
汁と思って飲んどったらええわって、飲んではいたんですけど。
でも、今まで食っとった味噌が当たり前だと思っとって」
東京で、実家の味に気づいた。
「人手が足りないから、手伝ってくれないか?」
母さんの頼みに背中を押され、押渕に帰ってきた。
誰かがやらなきゃ。だから、自分がやる。
庄下糀屋で使っている米はすべて、庄下家の田んぼで収穫したもの。
そしてそのお米は、途絶えることなく受け継いできた種だ。
「うちには代々受け継いできた種がある。
収穫した稲を使い切らずに種を残し、その分をまた次の年に植える。
品種としてはコシヒカリだけど、うちは自分の米を作り続けてる」
一度途絶えたら全部、なくなる。
それを受け継いでいくことこそ、いま生きている人間たちの責任なのだ。
南伊勢でたったひとつの糀屋。
廃れていく糀の世界。
「誰かが継いでかんとなくなってく。
醸造っていうのは日本の伝統的なものなんで、なくしたくなかった」
その危機感は、人が減り続ける地元・押渕の姿とも重なった。
田んぼを耕すのは、地域で庄下糀屋ただひとつなのだ。
「人がいなくなった田んぼは引き取って、自分らで耕す。
耕す田んぼはどんどん増えてったけど、田んぼがなくなると蛍もカエルもいなくなる。
昔の風景も自分らが守っとんのかな」
守りたいものがある。
それは、人間が土地に根ざして暮らす理由なのか。
真史さんが最後に言った言葉が耳に残った。
「でもなにより、うちの仕事をなくしたくなかった」
その声に迷いはなかった。
真史さんの背中が、とてつもなく大きくみえた。

守らなければならない味を、再現する。
味噌づくりは、女性の仕事としてのルーツがある。
昔は、家庭で味噌を作るのが当たり前だった。
家の外で働く男たちの代わりに、家の中で女の人がする仕事。
それが味噌づくりであり、糀づくりだった。
庄下糀屋も、初代から四代目までは女性。
真史さんが初めて、男の人として後を継いだ。

味噌をつくるレシピは、初代から変わらない。
完成した糀に水と塩・大豆を加え、一年間寝かせれば味噌になる。
混ぜ込む糀の量を増やすと甘くなり、水の量が違えば食感が変わる。
「うちの味噌をずっと使ってきとる人は、味が変わると気づく。
先代と一緒のようにはしてるけど、前から食べとった人には変わったと言われる。
変わるといかんから、そこらへんはええようにしとるけど」
今までつくっていた人が死ぬと、味噌がまずくなる。
そんな言い伝えがあるほど、味噌の味は繊細だ。
以前、庄下家の味噌の完成を待つお客さんに急かされ、焦って出したことがあった。
できた味噌は、味が違った。
お客さんに言われて、もう一度混ぜ直した。
「地元でうちの味噌使ってもらってる人たちがいるもんで。
毎日使ってた味噌が食べれんかったらあかん」
庄下糀屋の加減がつくりだす味噌の味は、簡単に変えてはならない。
毎日食べるものだからこそ、食卓の味の基本になる。
味噌って、そういうものだ。
受け継いだものを、さらに次へ。
庄下家では一日一杯、必ず味噌汁を食べる。
それは規則と呼ぶものではなく、庄下家の日常であり、習慣だった。
「味噌汁なんか飲まんでパン買ってくる時代やで。
うちの子らも朝、「パン!」って言って起きてくるでさ。
パンはパンでいいんさ。
でもそれやったら、夜に味噌汁飲ます。
食っていうのはやっぱり大事やから」
食文化は、時代とともに変わる。
変わり続けるもののなかで変わらないものをつくる糀屋には、子どもに伝えたいことがある。

四世代が一緒に生活を営む庄下家。
真史さんが仕事をする姿を、子どももまた眺めていた。
「みせとくってだけでもこういう仕事に繋がってくる。
自分の子どもがこれをするかって言ったらわからんすけど、
言うてもらったら嬉しいかなと思います」
時代は変わる。人も変わる。地域も変わる。
変わり続ける時代だからこそ、昔から受け継がれているものに価値がある。
「糀づくりは周りで誰もやっていないことなので、やりがいはありますけどね」
いつかきっと、子どもが味噌汁の味を思い出す日がくる。
味噌汁の物語が受け継がれるその日まで、真史さんは庄下家の味を守り続ける。
三重県南伊勢町の漁村に移り住み、漁師&情報発信をしていました。現在は県外在住。