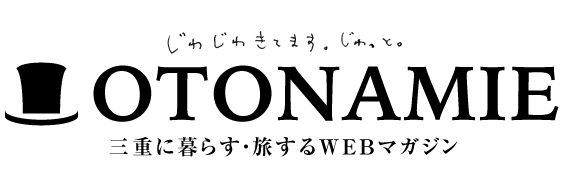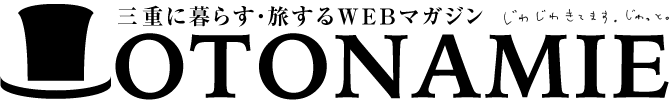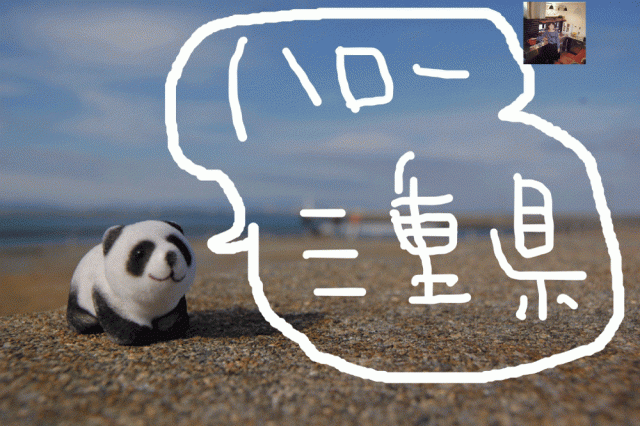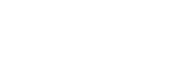一年前の秋頃、家族で山に登った。
知り合いが教えてくれた、経ヶ峰という、津市内の小さな山だ。
体力に自信がないので疲労が伴いそうなアクティビティにはととことん後ろ向きだ。体力に自信がないのに我が家には元気盛りの子どもが3人もいるから常に温存に余念がない。体力を奪うあらゆることを避けて生きている。
なのに、山に登ったのだ。あの日の私はとても勇敢だったと思う。
「今日山登りしない?」
唐突に夫が言った。
夫が休日の予定を提案することだけでも珍しいのに、脈絡のない「山登り」に度肝を抜かれた。
話を聞けば職場の誰それさんが山登りをして楽しかったという話を聞いたらしい。おおよそそんなところだとは思ったけれど、それにしても山登りってあまりに唐突だ。
もっと、こう、我が家にとって文脈のあるアクティビティが他にもあるでしょう。
下の子が当時まだ4歳で、少々心もとなくもあったし、確かみんな季節の変わり目で体調もどこか不安定だった。そもそも「山登り」と聞くだけでなんだか頑健な人間の特殊な遊び、という先入観が付きまとう。体育の時間が何より嫌いだった私にとって、なんだかとても遠い感じがする。たった45分の授業で心を砕いていたのに、山なんて登ったら降りてこないといけないではないか。途中で寝たくなったりお風呂に入りたくなったりしたらどうしたらいいの。
私がいくら煮え切らない反応をしても、夫は依然やる気に満ちていて、いやしかし、と押し問答を繰り返した結果、何とか翌週に引き延ばすことしかかなわず、その翌週子どもたちの装備を整えて山へ行くことになった。
*
私だってお母さんのはしくれだし、夫のこともそれなりに好きなので、いくら気乗りがしないと言ったって、楽しむつもりもある。
次の週末、たくさん握ったゆかりおにぎりを夫のリュックに詰め込んで、ぱんぱんに着ぶくれして、子どもたちにもこれでもかと着こませて、ファンシーな靴を履きたがる末っ子をなだめすかして運動靴を履かせて、上着を置いて行こうとする長男を説得して、8悶着ぐらいしていざ山へ。
登山口、と呼ばれる場所までは車で行く。
到着したそこは、もうすでに私にとってはれっきとした山そのものだった。私はここからさらに山の中へ、頂上を目指して歩いていくらしい。
すでに登山口で肌寒いのに、これからろくに日の当たらない山道を歩いて、ふきっさらしの頂上を目指すと思うと、想像だけでうんと寒くなった。
登山口には山の水らしきものを引いたパイプが突き出していて、そこから澄んだ水が流れていて少しだけ元気が出た。
寒いのも疲れるのも嫌いだけど、水は好きなのだ。水を見ればなぜか元気が出る。前世は水辺の苔か何かだったのかもしれない。
*
ひたすら傾斜を登り続けた。
子どもたちは、小人がいるかもしれないやら、かっこいい枝が落ちているやら、蛇行しながら元気に歩いていく。私は子どもたちが転がり落ちないか気が気でなく、ただ心配ばかりして歩いた。
随分と歩いたな、と思ったあたりで、急に開けた場所に出た。
地蔵がたくさん並んでいる広場のような場所だった。こんなところに、まあ、と驚いていたら側にお年寄りが3名ほど座っていた。
なにを話したかよく覚えていないのだけど、登山に来たの?とかそんな言葉を少し交わした気がする。彼ら同士は祭りだかなんだかの準備の段取りを話しているようだった。
私にとってそこは随分と山奥で、それなりに辺境と言ってもいい場所だったのだけど、ご近所らしき人が暮らしの延長のような振る舞いでそこに居ることが異次元だった。彼らのほうが私より丈夫であることは明らかだ。健康寿命という四字熟語だけが漠然と浮かんで脳裏を占める。
とりあえず、頂上を目指そう。
それが強い足腰の第一歩だと思うことにして、彼らに別れを告げて、また歩き出した。
*
ハイキングコースとは名ばかりで、私たちが歩いたのは思った以上にきちんと山道だった。私がこれまでの人生でハイキングだと信じていたものはもっと牧歌的でのんびりとしたものだけど、今歩いている道は時折不安になるほど細くなるし、たまに崖では?と思うほど切り立った道になったりもした。それでもたまにすれ違う人がいるのでそれを心の支えにしてまた登る。そんな繰り返しでひたすら登る。
頂上からの景色がとてもいいらしい、という情報だけを楽しみにただ登った。
やがて、少し広い舗装された道に出た。
登山道を案内する大きな看板とその下に丸太でこしらえたベンチのようなものがあり、おにぎりを出して座ってみんなで食べた。
おにぎりを食べながらどれ、と看板を見る。
我々はほんとうに随分と歩いてきたから、勘定ではあと30分のはず。
と、思っていたのだけど、地図をどう見てもなにかがおかしい。
地図によると私たちがいるのは標高でいうと、出発した登山道と変わらない。
そんな馬鹿な。ここまで膝を酷使して歩いてきたというのに。
夫とああでもないこうでもない、と見方を変えては地図を眺めるのだけど、やはりどう見ても、頂上までは遥か彼方であるらしかった。
私たちは、山を真横に横切っていいた。
これだから素人の山登りは、と思ったりはしない。むしろ想定内だ。山の頂上なんて大それたものを、私みたいな軟弱な人間があっさりと拝めてはいけないのだ。まずは横ばいくらいでちょうどいい。それが身の丈というものだ。
子どもたちの誰かしらがおにぎりを食べて腸が刺激されたのか、「トイレに行きたいよう」と言い出した。
またある子は、「まだまだ頂上を目指したいよう」と言った。
どうすればいいやら考えている間にも便意をもよおした子どもが緊急なのは明白で、その日は大人しく下山することにした。
*
頂上が見たかったと帰路も言い続けたのは確か長男で、またいつか登ろうね、と言ってなだめながら帰りを急ぐ。
あの、地蔵がたくさん並んでいた広場まで戻らないとトイレがない。
帰路はひたすらトイレを目指す、わき目もふらず、ひたすらに。往路よりも圧倒的に目的が明確で明瞭だった。
私たちは今、トイレを目指している。そのことがなんだかとても健全に思えた。子どもの排泄のために力を振り絞るというのは太古の昔からのあるべき親の姿という感じがしませんか。
あの日、私の運動靴は底がベロンと剥けてダメになってしまった。汚れてもいいランニング用の運動靴はそれ1足しかなく、次に山に登るときにはそれなりの頑丈な靴が必要だな、と思っている。
また登ろうね、と息子に言ったのに、新しい靴を買うのも億劫だし然るべき下調べをするのも億劫でついその気になれずにいる。
それでも時々、「頂上の景色がいいらしい」というまた聞きした誰かの言葉を思い出しては、たまに「またいつか」と思う。
春になったらまた登るかもしれない。
8歳、6歳、4歳の3児の母です。ライターをしています。